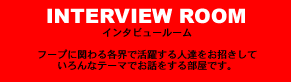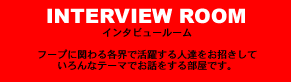|
このインタビューは僕からの強い強い希望で実現しました。
今回この無謀なリクエストに佐野さんはいとも簡単にOKしてくれた。
この対談は5月の連休の真っ直中、横浜のレコーディングスタジオでミックス作業の真っ最中に佐野さんに無理を言って収録したものです。
実際はムービーを回していたのだけれど、ここに掲載したテキストはそれを編集しないでノーカットで(まさにドキュメント)抜き出したものです。
通常はインタビュー記事は、編集者によって読みやすく書き換えられたりするものだけど、今回は特別に、ほとんど会話に近いかたちで掲載することを佐野さんから許してもらえました。
感謝。 林ワタル
2001年5月 横浜にて
佐野元春(以下、佐野):ロック音楽の映像というと多くの人は、例えばザ・ビートルズの「レット・イット・ビー」だとかストーンズのオルタモントだとか、ウッドストック、マーティン・スコセッシの「ラストワルツ」。それとデヴィッド・ボウイの60年代のドキュメンタリー。あのあたりを思い浮かべる人が多いと思うけどね。
最近のものでいうと、ジム・ジャームッシュやニール・ヤングと彼のバンドのドキュメンタリー。
僕もニール・ヤングというミュージシャンが好きだし、公開されるのと同時に僕も観に行った。
いいなぁと思ったのは、ジム・ジャームッシュの視点とジム・ジャームッシュ自体が、まぁニール・ヤングの方が年上なんだけれども、ジム・ジャームッシュというフィルムメイカーがすでにニール・ヤングの音楽にリスペクトがある。
だから観ていてすごく、いちいち納得がいくというか。
僕ももちろんニール・ヤングにリスペクトがあるわけだから、同じ視点でもってそのニール・ヤングのドキュメンタリーを観ることが出来る。
だからまず、どうなんだろう、ロック音楽を題材として撮る映画の基本的な条件としては、撮る側の監督なりね、スクリプターなりプロデューサー等が、その対象の音楽にリスペクトがあるのか、ないのか。
逆に言うとリスペクトじゃなくて、もの凄い憎しみがあってもドキュメントとしておもしろくなると思うんだよ。
とにかく普通じゃない思いがあるかないか、その対象に対してね。
ここが大事というか、そのドキュメントがおもしろいかおもしろくなくなるかの別 れ目になるんじゃないかと。
林ワタル(以下、林):佐野さんは劇映画のような作られた物よりはドキュメンタリー志向の物の方がお好きですか?
佐野:そうだね、10代20代の頃はそういう楽しくね、ポップな作り物の方がおもしろいなと思っていたけれど、最近はどちらかというとドキュメンタリーの方がおもしろいなって思うよ。
林:例えばさっき佐野さんがおっしゃったように、ドキュメンタリーは観る方の視点が何処にあるかが一番大きなポイントになるのだと思うんですけど、僕なんか佐野さんのドキュメンタリーを撮っていて、とても興味があるし覗いてみたいという心理があるし、そこで演出するしないという部分が、かなりのドキュメンタリーに対して大きなポイントになってくると思うですけど、佐野さんが逆に自分がドキュメンタリーを撮るとした場合に、どんなものを撮りたいですか?
佐野:僕はやはり、僕が愛情かもしくは憎しみかを注げる対象を、ドキュメントする対象としてセットしたいよね。中途半端な気持ちの物は、結局結果中途半端な物になってしまうと思う。
もの凄く愛しているか、もの凄く憎んでいるかどっちかを対象として取り上げたいと思う。
僕は音楽家なんで、実際のフィルムメイカー達のさまざま苦労とか横に置いておいて勝手に言ってるけどもね。
そして俺が撮るんだから俺の視点でやらせてもらうよっていうかんじだよね。
そして観てる人もさまざまなご意見があるでしょうけれども、僕はこういう風にしか見えない、というのをちぎっては投げちぎっては投げするね、もし僕がドキュメントを撮るとするとしてね。
何故ならばドキュメントというのは、真実をえぐり出す物では無いと僕は思ってるの。
林:うーん。
佐野:ある個人の、ある観察者の特別な、個的な、物の見方の発表物というか。
真実っていうのはもっと別のところに僕はあると思ってる。
1人のフィルムメイカーによって真実が暴けるかといったらば、近くまでは近寄れる
けれども、
真実を暴けるかといったら、僕はノーと言うね。
真実はそう簡単には手に入らないよね。
|